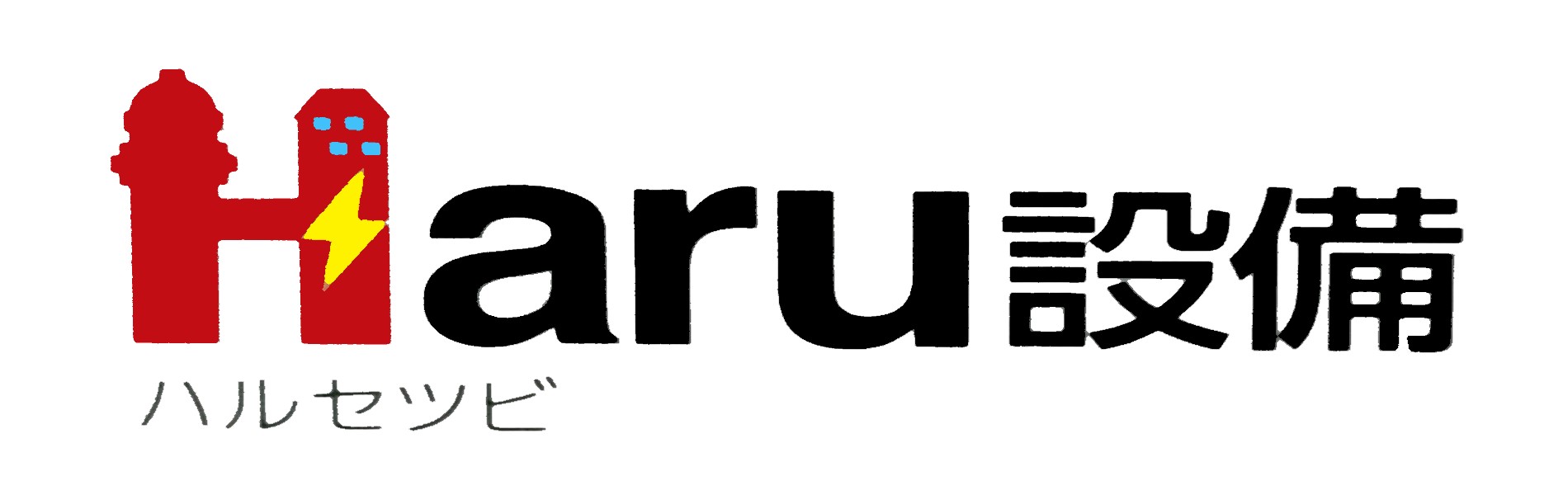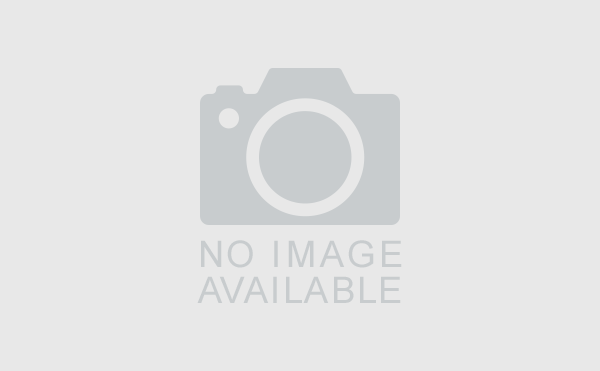住宅用情報盤(インターホン)の勉強
インターホン工事と火災報知設備の関連性は非常に深く、工事のお手伝いに行きながら覚えられることはどんどん覚えていきたいと思いお手伝いに参加させていただいています。
最初は色々基礎を学んできて非常にレベルが上がったなと思っているのですが、15回目の応援でもっと自分で調べて行かないとこれ以上の進歩は無いなと思い始めました。
もちろん、工事として線の圧着や接続はやればやるほど身に付く物ですが、インターホンの知識としては室内の本体設置前にまだまだ調べれば得られることは多いハズと思ったのですが、配線説明書も見ていてもなんだか的を射てないような雲をつかむような内容です。(実際に個人で接続用と思ったら出来るのでしょうが、知らないお宅に設置してある物を見ても役に立てなさそう)
如何したら、インターホンの工事をやらずに設置出来うるレベルに達することが出来るか考えた結果、次の事をしらべてみようと思います。
【どのような商品を訴求して売り込んでいるのか調べる事で、関連の製品と機能をしらべる】
幸いアイホン株式会社の工事に特化した会社に手伝いに行っているので、設置する製品から関連商品をしらべ、どのような物を付けられるか?、警報は?と言った視点から端子を確認してみたいと思います。
シリーズ
アイホン株式会社の売り出している集合住宅インターホンシステムは次のようなシリーズが有りました
それぞれの製品の解説については改めて調べてみますが、ハイエンド、ミドルレンジ、エントリーモデルでのすみわけがなされているようです、性能の差をどこで付けているか気になるところです。
今回はこのシリーズ
dearis(ディアリス)と言う製品をいつも取り付けており、比較的多様なオプションを取り付けられるようです。
取り付けられるオプションが多ければ配線数も増えるので、交換前の製品が埋め込みか露出なのかで設置レベルが上がりそうです、線は2C1.6が電源として一本、そのほかの線は太くても3C1.2で多くは4C0.9ですが、数が増えれば当然収まりにくくなり難易度が上がります。
関連機器接続図
関連機器一覧
いつもは施工説明書をみて、今回はこの線を使ったのかな?とか考えていたのですが、得るものが無かったです、しかしこのシステム系統図を見たらなるほどと思えました。
室内親機に接続することが出来る製品は次の通り
- マグネットスイッチ(玄関) 配線 AE0.9-2C
- マグネットスイッチ(バルコニー) 配線 AE0.9-2C
- ガスCO2 警報器 配線 AE0.9-2C
- コールボタン(トイレ) 配線 AE0.9-2C
- コールボタン(浴室) 配線 AE0.9-2C
- 玄関子機 配線 HP0.9-3C
- 集合玄関機 配線 FCPEV0.9-1P
- 火災感知器 AE0.9-4C
- 人体感知センサー 配線 AE0.9-2C
- ワイヤレス受信機 AE0.9-4C
- 漏水センサー AE0.9-2C
注目ポイント
書き出してみて気が付いたことは
防犯に使うマグネットスイッチは閉じている時は窓と窓枠でマグネットがくっ付いて、開くときにマグネットが外れ信号が行くのでB接?なのかもしれない。AE線
漏水センサーも水が漏れたら接点繋がるのでB接のような・・・。
ガス警報器は直接100Vの電線で電力を供給しながら信号線で信号を送るようになっていた。AE線
コールボタンは押したら接点閉じるからA接だろうAE線
玄関子機は耐火線(HP線)なので火災の際は最後まで親機からの緊急音声を玄関から出し続ける事が出来る
集合玄関機に接続する住戸アダブターへは専用のFCPEV0.9-1P線を使う、(着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)と言う名称だが、電話回線や制御回路などに使われる線で、被膜がゴージャスな感じで電磁波をブロックし周りの電線の干渉を受けにくいようです。
ワイヤレス受信機が4Cなのはなぜだかわからない・・・
火災感知器は中継器を挟み、隣の警戒区域で端子台を経由しながらつながっているAE線
こうやってみると施工説明書の端子の使い方がだいぶ理解できたような気がします。
B接とか説明書に書いてあったかな?・・・