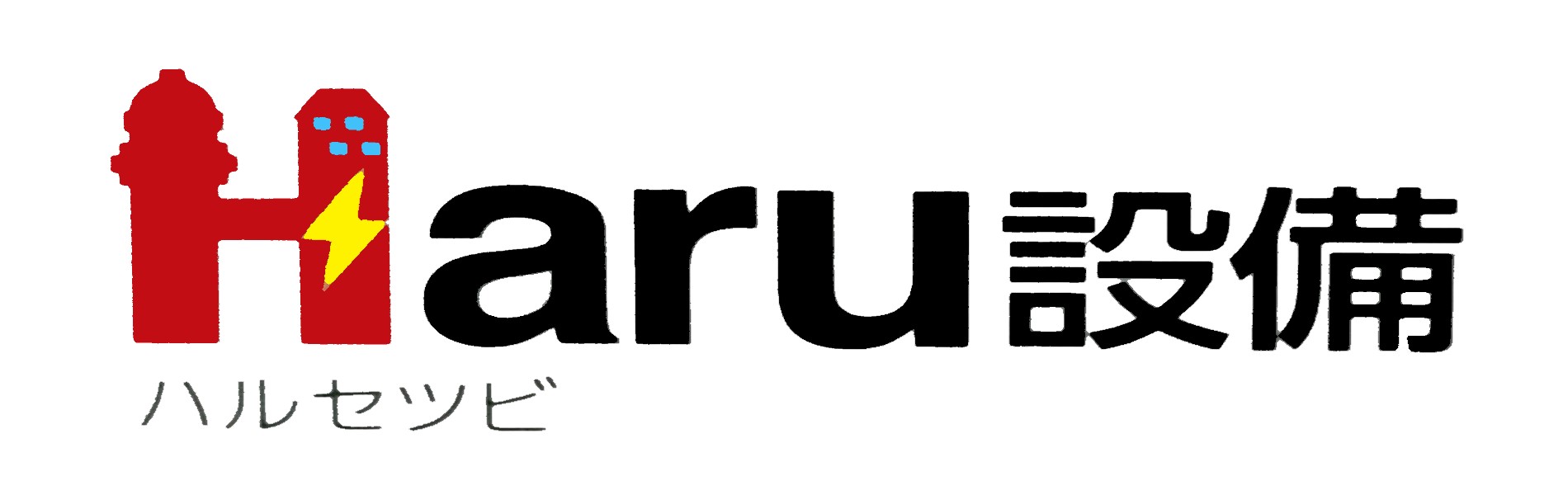泡消火設備の配管工事2
連続で泡消火設備の配管工事のお手伝いに行ってきました、本日で三日目という事で残念ながら二日目の一斉開放弁設置には立ち会えませんでしたが、新しい一斉開放弁に変わっており、コンパクトになっていました。
本日は手起動装置から一斉開放弁までの配管と消火ポンプと泡消火薬剤貯蔵タンク周りの配管を設置しました。
私の主な仕事は配管のカットとねじ切りでみんなが使う配管をせっせと作成していました、親方がの指導が解りやすく、危険な機器ですが安心して作業できました。
ねじ切りき
初めてお目にかかる道具で電動でおネジを作り、エルボーやフランジなどと組み合わせ好きな長さで配管を接続する為に必須な道具です。
電動パイプのこぎりできっちり指定の長さに切った配管を両側共にねじ切りでネジを切っていきます。
鋼鉄の配管ですから、ユックリ強い力で管を削り、熱を抑えスムーズに削れるように自動でオイルが掛かる仕組みとなっていました、これが有れば配管は自由自在だなぁと感じました、配管工事業も面白そう。
配管の太さ
一番気になっていたのが、資格試験でも出る配管の太さですが、ヘッドの数に応じた太さがポイントになります、流量により変わるのですが、分岐をするときその分岐後のヘッド数に応じ2個以下なら25A、この25Aが一番細くつまりヘッドに接続している配管となります。
3個以下なら32Aで5以下なら40Aとなっています、現場で確認させていただ来ましたが、ヘッドから見ると良くわかる配管径になっていました。
ちなみに径が大きくなると重量も増加し、ネジ締めもパイプレンチをうまく使わないと閉められず、帰る頃には腕周りがパンパンになっていました。
まとめ
消防設備士の水系を受ける人はこういった経験があると楽に取得できそうだなぁと思いました、仕事としては配管が鋼鉄製で消火ポンプに近いほど短くても一人では接続できないような重さゆえに点検作業と比べれば格段に疲れます、しかし図った長さがぴたりとはまった感じや漏れなく水が流れた時の達成感は非常にうれしいです、これでお金がもらえるわけですからおすすめの仕事です。