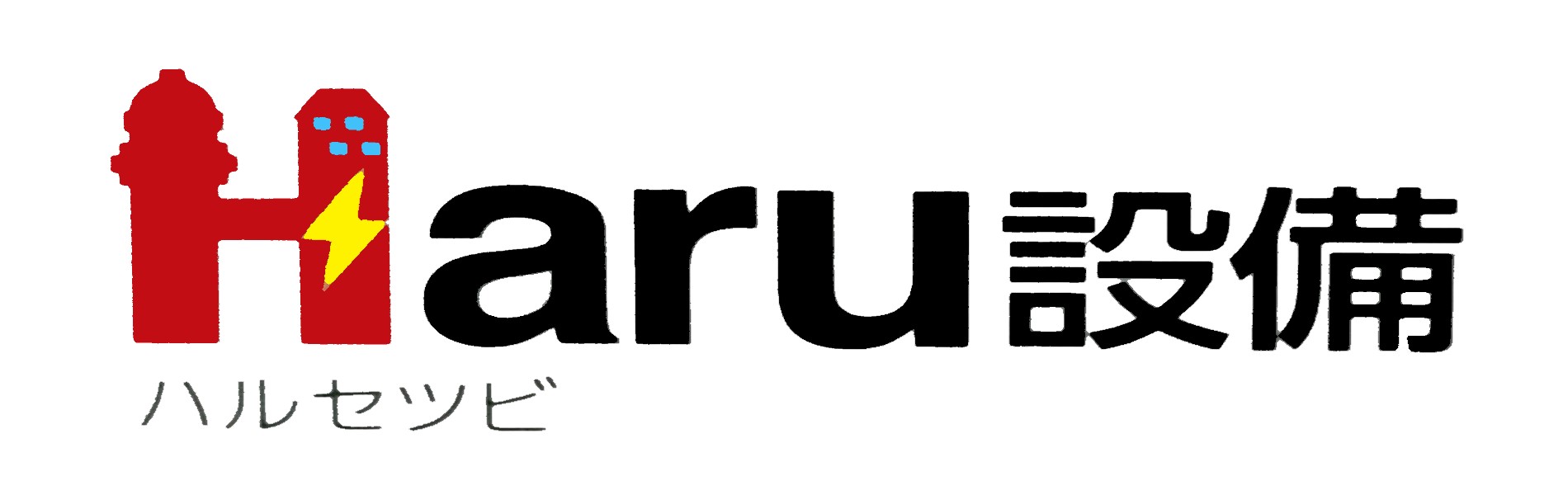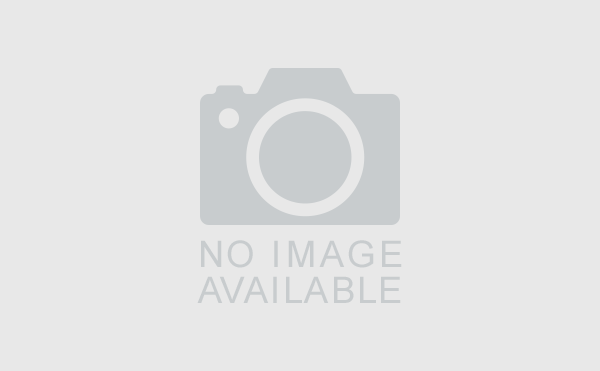漏電火災警報器の不良
最近漏電火災警報器の点検を見る事が増えてきました。
専用の漏電火災警報器試験機を用いて、変流器に電流を10mA刻みで流していく事で疑似的な漏電を起こして警報器が働くか確認をするのですが、20年経過の漏電火災警報器が多く存在しており、そろそろ不具合が出るか出ないかと心配しながら点検をしています。
先日の物件では10mAで発報と感度良すぎな警報器が有り、こりゃー交換が必要だろうなと考えていましたが、この事に対して色々疑問に感じたので調べてみました。
漏電警報器の仕組み
変流器を通して、いわゆる「漏れ電流」を計測することで漏電火災の原因となる漏電をしらべるのですが、電柱から来た電線の電流はLを通ってCから電柱に戻っていくイメージです。このLとCを変流器で囲う事で行き帰りの電流量を監視しているのですが、この時に何らかの原因で変流器を通った後に地面に流れて電柱に戻ると、Lで計測した電流が少なくなってCに戻ってくる現象が起きます。何らかの原因がいわゆる漏電以外になく漏れ電流が一定数を超えた際に警報を出して、建物の漏電を知らせる仕組みです。
漏電なのか漏電火災警報器の不良なのか?
これが最大のポイントで、変流器に試験機を使って疑似漏電を起こした際、通常は200mAで警報が鳴る様設定されています、建物全体では20~30mA程度は微々たる漏電が起きていると仮定して、120mA程度で警報が鳴るのが正常と判断する基準なのですが、10mAで警報が鳴るという事はすでに190mAの漏れ電流(漏電)が発生していると仮定できます、ここで消防設備点検的には不良と上げたいところです。
漏れ電流計と言うクランプ型の機器が有り、電線を挟む事で現在の漏れ電流を測る機器が有るので、こちらを使えば漏電量が計測できるので交換前にチェックすると、機器が原因か漏電が原因か判別することが出来ます。
しかし、一般的には漏電ブレーカーと言う漏電を感知する機器が取り付けられているので、こちらの漏電ブレーカーは一般的な物であれば30mAで作動して、停電するようになっています、ただ漏電ブレーカーが無い物件では上記のような疑問や疑いを持つことが事故の早期発見になると思います。