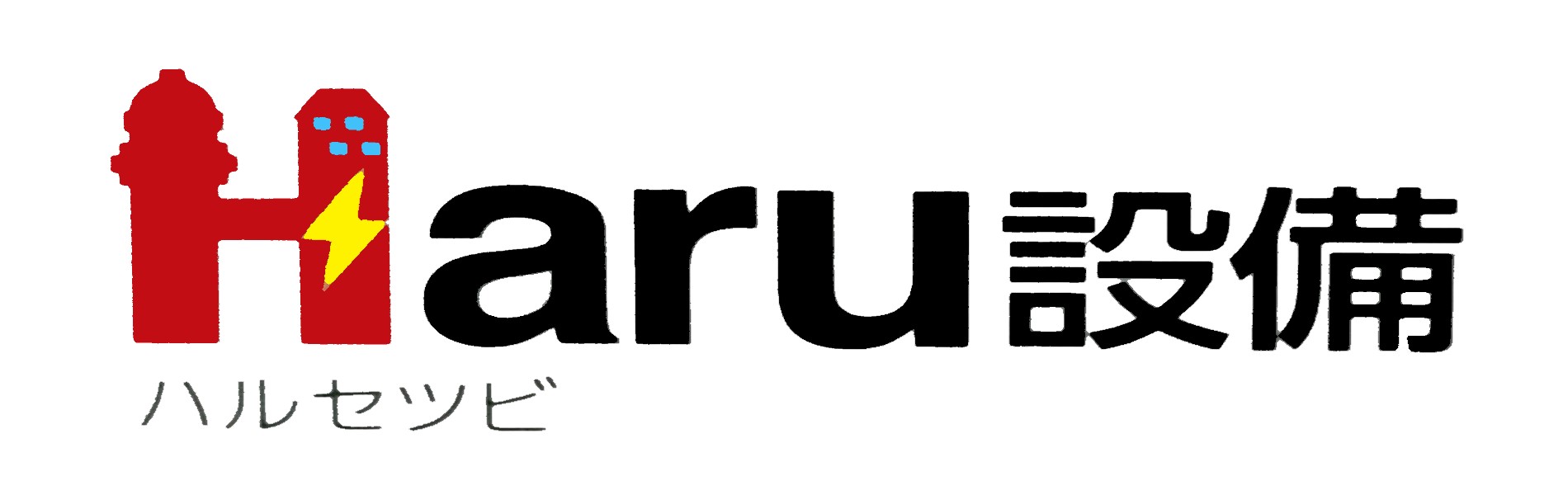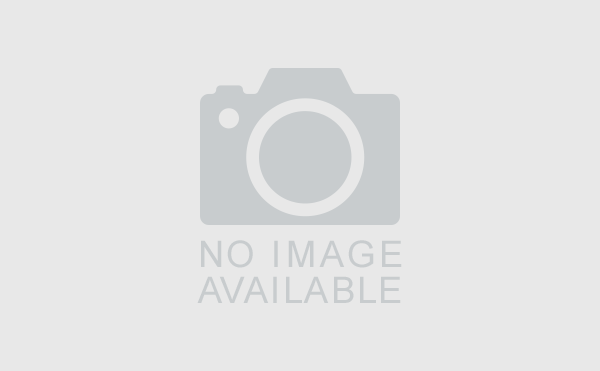誘導灯交換工事
先日は学校体育館の誘導灯交換工事を行いました、まだ3月末の事ですが夏日の工事でしたが、正門の桜の花が帰る頃には5分咲き位になって疲れも和らぎました。
体育館の二階フロアーのサウナはさておき、苦戦も良い経験になり次回の交換時に生かせそうです。
誘導灯の工事ポイント
その場に適した標識の設置
材料の受け取り時には特に受け取る標識パネルが一番のポイントだと思います。
リニューアルプレートも勿論、無いと固定がそもそも出来ないので取り付ける事が出来ないわけですが、交換終わって最後に避難口付けようと思ったら矢印だったらとなったら復旧するしかないです。
正しい標識を預かっているか特に注意しましょう。
撤去ーアンカーの確認と電力の確認
まずは撤去ですが、古い誘導灯の種類に応じた解体をして、アンカーと電線をむき出しにし、①どのような方法でつり下がっているか②電源は渡ってないかを確認します。
アンカーでつり下がっているか、新設の金具と同様のプレートで下がっているか、の2通りなので、アンカーの場合はボルトとワッシャーは無くさない様にしましょう。
アンカーでつっている場合はリニューアルプレートが必須でこちらを活用し設置ベースを作成する感じですね。
渡り配線だった場合は渡り線が付いていないので、新設の誘導灯も同様に渡り線を外しておきます。
準備ー電線の長さとL線N線の確認
そして、電線を切断する前に長さ一応見ておきましょう、短いようなら圧着で延長ですね!
古い誘導灯工事で使用している電線は白赤の場合もありますが、それでも白はニュートラル線赤はライン線ですが、古い機器に刺さっていた場所も一応チェックすると良いです。
そのためには電線は切断して交換すると、どの穴に何色が入っていたか証拠が残せますので安心です。
設置ー固定方法と水平
アンカー固定の場合リニューアルプレートと全ネジの長さが合わないと設置できないので時には全ネジを少し切るか、短めの全ネジを用意しておき長さ調整が出来る様にした方が良いです。
リニューアルプレートを水平垂直に固定できれば次は誘導法本体をプレートに固定する作業です、水平機を使って真っ直ぐ設置するのがポイントです。
手元のスペースや電線の長さがあるなら活線のまま出来るとスムーズですが、短絡したときの為にブレーカーの場所は押さえておくべきです。
真っ直ぐ固定出来たら、正しい標識とライト、バッテリーを固定して完了です。
まとめ
多分ですが、同じ業者さんが一番最初に誘導灯を取り付けているはずなので、一ヶ所取り付ける事が出来れば、そのあとの作業は同じ方法で取り付けている事が殆どなので作業も楽になっていきます。
時間に余裕をもって設置に行きましたが、とにかく一台目を付けるのが一番時間が掛かっています。
しかし、この経験で最初の一台目の時間も短縮できると思うので次回設置が楽しみです。