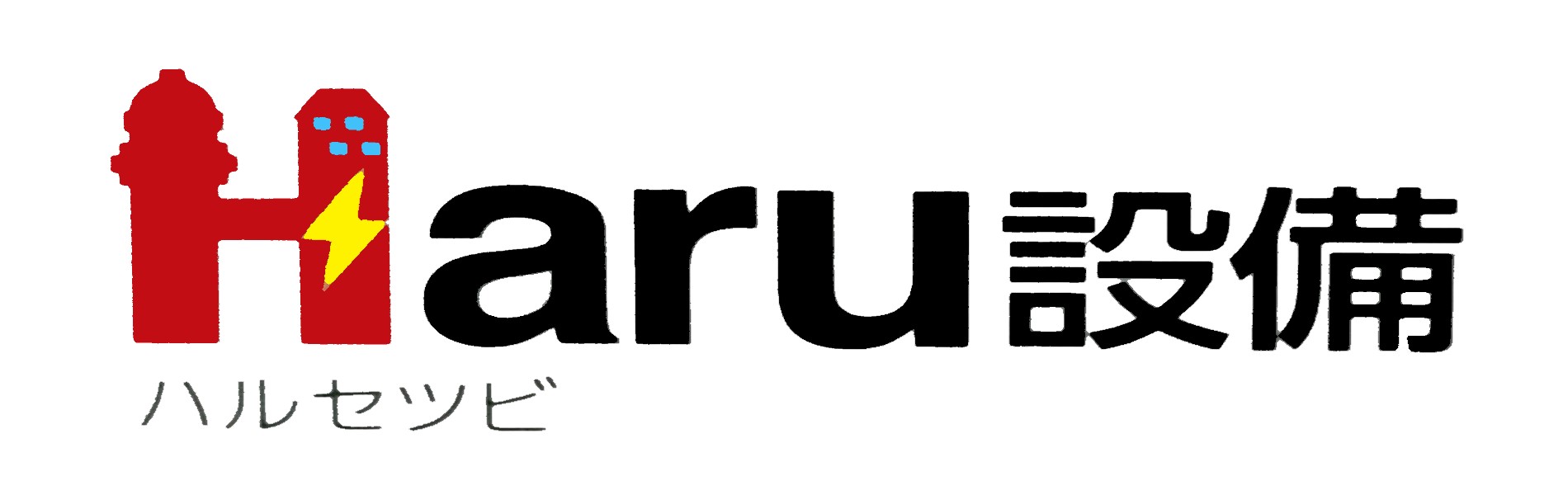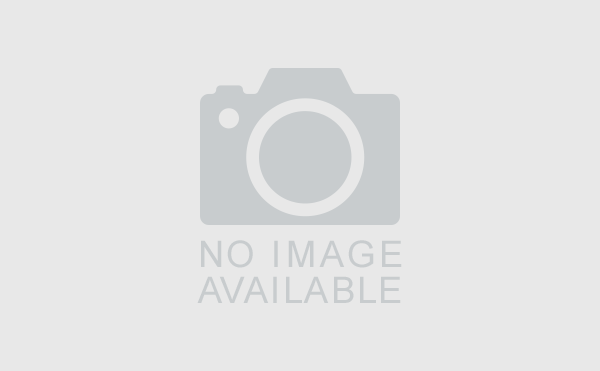三回目甲2試験行ってきました
三回目になる甲2試験は結果はどうであれ、今まで勉強で蓄積できた知識が活かされた感じでした。
三回目ともなると毎回つまずく問題も決まっている事がわかってしまい、もし四回目が有るなら次回はその点をしっかり覚えておきたいと思いました、その問題ですが
法令は簡単
さすがに三回目ともなると、法令位は朝飯前、埋まらない解らない問題はほぼなしです。
設置基準だけではなく、薬剤の決まり事や高さ・距離の基準など幅広くでますが、暗記でカバーできます。
構造機能工事整備(機械)も何とか
機能で必ず一問溶接が出てるのが苦手ですが、必ず出るので覚えておけばボーナス問題になります。私は毎回パスしてます・・・
流水検知装置の詳しいルールも苦手で、なんだかこんなに詳しくテキストに書いていたかと思う位正しいor誤った選択問題がでます。
ただこちらも一通り低発泡高発泡についてや固定式移動式の問題、薬剤の問題、とう幅広くは出ます。
規格の問題は4問だけが鬼門
4問だけの規格問題は毎回蓄電池やモーターの起動装置の問題がでます、電源落ちて40秒以内の問題は前回も出た気がします。
やはりポンプの不良原因も出ていました、規格の問題は毎回難しいと思います、掘り下げ方がエグイ気がします。
実技は面白い
毎回おもうのですが、実技を解くのが面白いと感じるくらいは勉強をしておきたいですね・
さて、問題では高発泡泡放出口(私は答えで高所泡放出口と書いてしまった)などの泡放出口や管継ぐ手類(フランジの名前が20分ぐらい出なかった)は高確率で、試験方法は泡試験コレクタを使って何する的な問題は必ず出てると思います。
図面では感知継ぐ手開放ヘッド併用平面式がでました。開放ヘッドを併用する場合は充水しているので一斉開放弁を使わず閉鎖ヘッドを使う奴ですね、手動起動も無いのは推測で、流水検知装置書くの忘れたのは痛い、そこだけだと問題数少ない為かポンプ、泡タンクの弁も記入しました。前回は全く使わなそうな燃料タンク周りの配線と配管だったので、その時よりはできたかなとおもいます。
まとめ
思い出しながら書いていると、受かったか不安になってきました、正答率はさておき答えを100%自信をもって埋めてきたので次は甲3の勉強をしていきたいと思います(二回目)