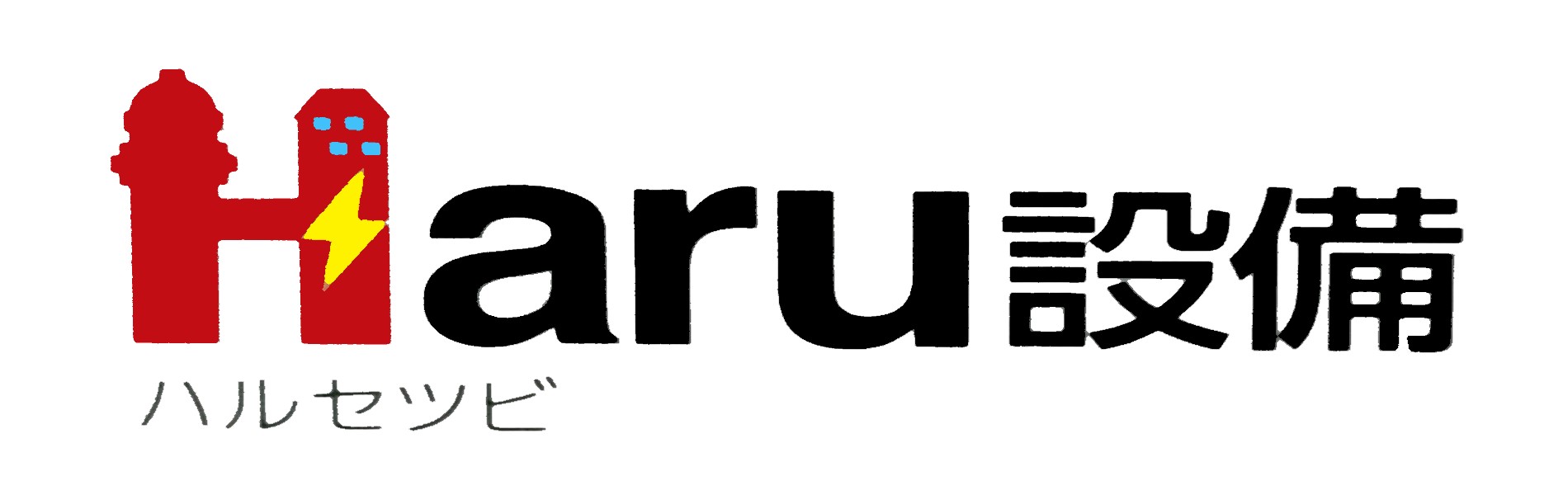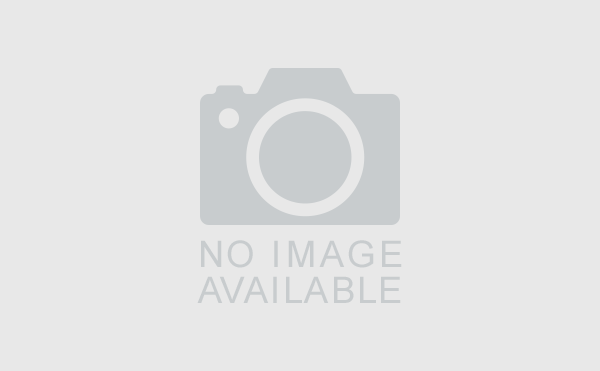共同住宅用自動火災報知設備
マンションを点検するに当たり自火報について改めて勉強し直し他ので残して置きたいと思います。
共同住宅⑸項ロは住戸ごとに自火報を付けているのをよく見かけます、鉄筋コンクリート製のマンションなら各戸で耐火構造となる為、延焼を防ぐ効果が高い事からと思われます。
管理人室の住棟受信機で一括してどの部屋で火災が発生しているか一目でわかり、関係しそうな場所のみで警報が鳴る仕組みなので、不要な混乱を避け、消火に当たれる考えられた設備となっています。
実際に自動火災報知設備と共同住宅用自動火災報知設備がどのように違うかをまとめてみます。
警戒区域
自火報だと警戒区域がP1受信機なら無制限に、P2受信機なら5回線まで設定できます。
共同住宅自火報なら各専有部及び共用部(集会所、管理室、倉庫、電気室、駐車場など)毎のエリアに分けて警戒区域を設定できます。
P1受信機を使った自火報との違いは広めの範囲を見る自火報と中継器を使ったエリア分けが出来る共同住宅用と言った感じです。
例えばP1受信機の自火報物件なら101、102、103号室で一警戒区域104、105、106号室で二警戒区域と言った感じで各室に4~5個の感知器が使えます(一警戒区域で16個まで)。
共同住宅自火報の物件なら、101号室で一警戒区域(150㎡以下)の中で各部屋に一個、またバス、収納部など必要に応じ設置可能となります。
警報区域
自火報なら、基本全体に警報が鳴る仕組みです(受信機の設定により、警報区域を分ける事が出来る)
共同住宅自火報なら、火災の発生した部屋及び同フロアと直上階のみで警報音が発報します。
詳しく分けると階段室型特定共同住宅と廊下型特定共同住宅と言うのが有り、エレベーターの昇降路や警戒区域に面する住戸など若干警報区域が異なるのですがここでは割愛します。
中継器
この中継器を使って各戸毎に警戒区域を作る様です、各フロアの総合盤の端子台を経由して、各部屋へ火災報知用の電線を入線し、室内または子機(玄関のインターホン)で室内への入線をするようですが、PS部に中継器が有ったり、屋根裏に隠れていたり、入線方法は色々ある様です。
この中継器の場所によってはリノベーション工事の際に結構な問題が発生する事もある様です。
まとめ
共同住宅用自動火災報知設備の他に住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備と言った物もあり、点検表が自動火災報知設備と別れるところが今回のブログに繋がっています、まだまだ調べたりないですが興味をもって取り組んでいきたいです。