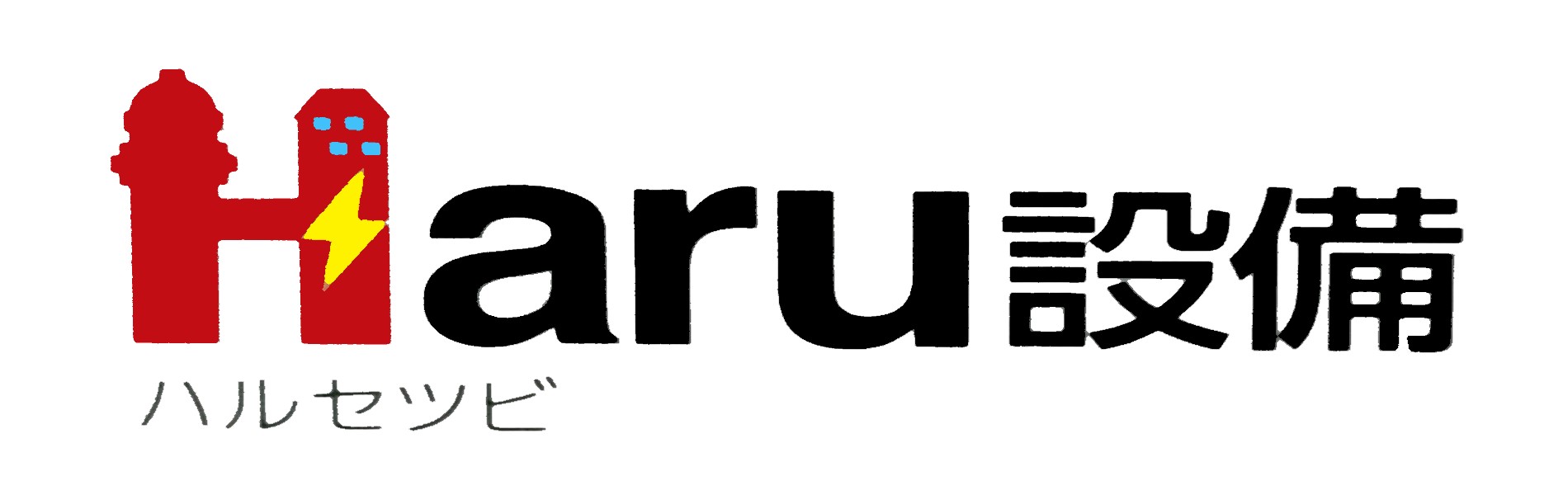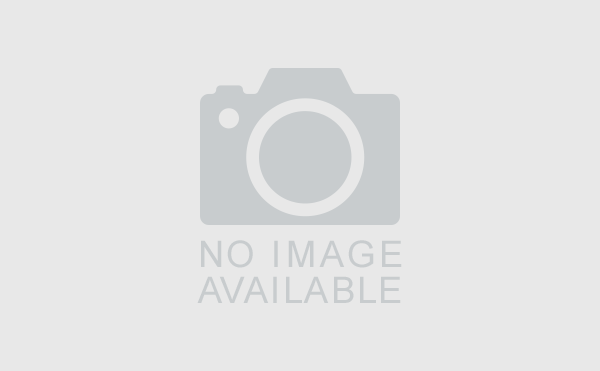甲3の資格試験
本日は甲3のテスト受けてきました、合格してるはずだ(遠い目)
また受ける可能性は無くても・・・受けるかもしれないので勉強する時のポイントを残して置こうと思います。
ちなみに私は免除しまくりで法令共通と基礎全部と構造・機能及び工事・整備電気はパスです。
法令類別
この試験の前に甲2を受けてきた事で非常に簡単に感じました、同じ3種消防設備という事で対応する対象物、危険物がかぶっています。
飛行機の格納庫が対象から外れて、道路、駐車場、車の修理場、危険物施設が残った感じで、火気を使うボイラーや電気設備、通信機室が対象になりました。
覚える対象物の面積と危険物が少し細かく分類されて覚える所は増えてはいますが、苦にならないレベルです。
構造・機能及び工事・整備の機械
今日受けたテストでは合金やら焼きならし、溶接は出なかったですが、管の素材が出てました、一問だけですが確か答えはSC管のSが一個多いのが誤った部分で(・m・ )クスッっときました・・・
ここは範囲が結構広い代わりに回答数も多いので意外と勉強してなくても答えを拾えました(テスト二回目だし一回目結構勉強したし)
各消火設備(不活性ガス、ハロン、粉末)の特性から、放射時間やら対応防火対象物、貯蔵量やら開口部やら各種弁など広いけどここを覚えないと実技の点とれません。
(勉強が嫌になった後半に気が付きましたが、細かな数値は実技の対策に移ったときに思い出しながら覚えるのが得策でした)
規格
ここ、いつも四問しか出なくて、これを3問外すと実技採点してくれないと思っていましたが、どうやら構造・機能及び工事・整備と同グループみたいで安心しました、ここも今回後半にきがつきましたが、出る所がハッキリしていました。
各弁、噴射ヘッド、音響、制御盤、自家発電、蓄電池、移動式のホースノズルもろもろが具体的に4問出ます。
弁が選択・放出・開閉弁・容器弁と併せて定圧作動装置、圧力調整期をパーツに至るまで覚える必要があり大体2問だけ出る、1問は非常電源関連、1問は移紛の1動作?2動作?で作動する構造(どっちだ?)とか。
らくらく解ける合格問題集のページの項目で勉強する場所を絞ると
実技
実技がえらい簡単でした、選択弁のルートを点線でせっせと引いたり、この時安全弁と逆止弁を記入する問題(問題は3個まで使って良いという内容で、すでに一個レリーズで使われていたのでひっかけ?)となんと移紛の機器説明を直接記入する問題でした(唯一点検をそこそここなした設備)
まとめ
次回受ける事はないハズですが、教科書と過去問やってこの文書を振り返れば、もう一周見る場所を無駄なく調べられると思います。
楽々わかる、楽々解けるの目次で勉強する場所を絞れば自分は1週間前勉強で行けるはずです。